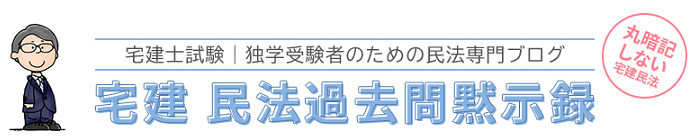|更新日 2023.9.11|公開日 2019.11.28
2021年の民法改正により、相隣関係や共有の規定が大きく変わりました。
改正法の施行時期は、2023年(令和5年)4月1日で、今年の試験範囲となります。
1 相隣関係の趣旨
隣りは何をする人ぞ 相隣関係というのは、隣接する不動産所有権の利用を調節する関係をいいます。土地・建物などの「不動産」は、自動車や家電などの「動産」と違って固定していて互いに隣接し合っています。そのため、1つの不動産の利用は、隣接する不動産の利用に何らかの影響を及ぼしているのが通常です。
こうした影響を無視して、隣同士の所有者が、互いに境界線いっぱいに絶対的支配権を主張して、たとえば境界ギリギリに建物を建てたりしては、かえってそれぞれの所有権の平和な行使が妨げられてしまい、社会の共同生活は困難となります。
そこで民法は、隣人同士の円満な共同生活のために「普通に生じる程度の影響」は互いに認容するよう、所有権相互の最小限度の譲り合いを求めているのです。
2 民法改正事項
3 その他の規制
1|境界標の設置
土地の所有者は、隣地所有者と共同の費用で境界標を設置することができます。境界標の「設置費用や保存費用」は、相隣者双方が1/2ずつ負担します。
ただし「測量の費用」は、土地の広さに応じて分担します。
2|境界線付近の観望制限
境界線から1m未満の距離に、他人の宅地を見通すことのできる窓または縁側・ベランダを設けるときは、目隠しを付けなければなりません。隣人のプライバシー保護のためです。
3|自然的排水の受忍義務
水が自然に高地から低地に流れるときは、高地の所有者は、低地に排水することになります。この場合、低地の所有者は、隣地から水が自然に流れてくるのを妨げてはならず、これを受忍する義務があります。
自然の流水を阻止するような「工作物を設置」することはできません。
4|境界線上の境界標等|共有の推定
隣接する土地の境界線上に設けた境界標、障壁、溝、堀などは、相隣者の共有に属するものと推定されます。
5|雨水を隣地に注ぐ工作物設置の禁止
土地の所有者は、直接に雨水を「隣地」に注ぐ屋根や工作物を設けてはならず、これに反した場合は、隣地所有者は、所有権に基づいて妨害排除または予防の請求をすることができます。
宅建民法講座|テーマ一覧